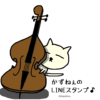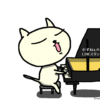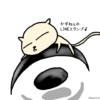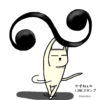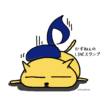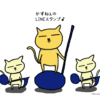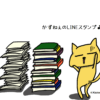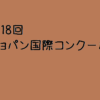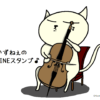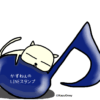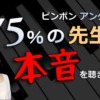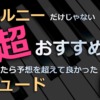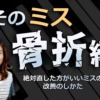【演奏の面白さはギャップにある】面白くない演奏の特徴と3つの改善策
今回は演奏の面白さはどういったところに現れるのかというお話です。
演奏がおもしろくない…
そう指摘されて、どうやったら面白い演奏になるのか悩んでいる人がこの記事にたどり着いたのではないかと思います。
この記事では「面白くない演奏」になってしまう理由と改善策について以下解説していきます。
- そもそも面白さって何?
- 面白い演奏の特徴
- 面白くない演奏の特徴
- 3つの改善策
- 楽曲分析をする
- 曲の雰囲気を表現する
- 表現のギャップをつける
色んな感覚や意見があります。
あくまでも一音楽家の一意見のブログエンタメとしてお楽しみください。
【演奏の面白さはギャップにある】面白くない演奏の特徴と3つの改善策

【演奏の面白さはギャップにある】面白くない演奏の特徴と3つの改善策
演奏の面白みとは抽象的な表現なので少しわかりにくい。
面白さを「人が興味をもつ」「心が動くこと」と仮定することで心の動きであることが分かります。
人の心の性質上どういったものに「面白さ」を感じる傾向があるのか。
これを知ることで演奏にも生かすことができ演奏が変わっていきます。
ここではあくまでもある一定レベル演奏ができる前提で、面白い演奏とは「人の心に作用する心理的なもの」としてお話していきます。
- そもそも面白さって何?
- 面白い演奏の特徴
- 面白くない演奏の特徴
- 3つの改善策
- 楽曲分析をする
- 曲の雰囲気を表現する
- 表現のギャップをつける
そもそも面白さって何?
面白さについての研究は、ダジャレや落語・万歳などにおいては研究されています。
またビジネスの世界でも人心掌握には「面白さ」は重要であるとされています。
ここでは人がおもしろさを感じることはこの2つ
- ギャップ(差異)
- 分かりやすさ(共感)
このギャップと分かりやすさを演奏に落とし込んでいきます。
面白い演奏の特徴
面白い演奏の特徴5つ
- 非流暢なフレージング
- ダイナミックレンジの差異
- 緊張と緩和の差異
- 意外なタイミング
- 分かりやすく伝わってくパフォーマンス
ハッとさせられたり、そうだよね!と思わさせられる演奏
面白くない演奏の特徴
面白くない演奏の特徴5つ
- 単調なフレージング
- 強弱の差がない
- どのパーツも同じ表現
- 変化のないタイミング
- 伝わりの弱いパフォーマンス
刺激が足りなくて退屈と感じる演奏
3つの改善策
演奏に「差異」と「共感」をつくるために必要な改善策を3つ解説します。
- 楽曲分析をする
- 曲の雰囲気を表現する
- 表現のギャップをつける
1と2は共感、3は差異です。
1. 楽曲分析をする
分析をすることで音楽の定型の認識を持てます。
- 楽曲の構成
- 和声
- 転調
- フレージング
理論が分かっていると「こう弾く」というのが共通認識が持てるので押さえておく
2. 曲の雰囲気を表現する
理論ばかりだと演奏が堅苦しくなります。
音楽に対してイメージをもつことは共通した認識をシェアしやすくなります。
雰囲気を掴んで表現するポイント
- 曲や音の質感
- テンポ感
- 音楽以外のものに例えたイメージ
自分で説明がつくイメージを持っておく。
言語化の訓練にもなる。
3. 表現のギャップをつける
分析やイメージは、それを表に出すひつようがあります。
ギャップを付けた演奏にするために必要なこと
- 弱い音と強い音の差をつける
- 表情のコントラスト
- cresc.やdimを効果的に表現する
楽譜上の指示だけでなく、楽譜の裏側の部分にある表現を読む(楽曲分析・和声を理解して)。
分析で得た情報をギャップを意識して表現。
間隔がつかめるとかなり効果的に面白みが増します。
まとめ
人がおもしろさを感じる「差異」と「共感」を切り口に、面白い演奏について以下を解説しました。
- そもそも面白さって何?
- 面白い演奏の特徴
- 面白くない演奏の特徴
- 3つの改善策
- 楽曲分析をする
- 曲がどういう雰囲気かを表現する
- 表現のギャップをつける
出来そうなことから取り入れてみてくださいね。
参考サイト&文献
- CiNii 駄洒落の面白さにおける要因の分析
- CiNii 隠喩的表現において"面白さ"を感じるメカニズム
- 論説「おもしろい」の法則
- 日経トレンド「面白い」とは“差異”と“共感”の両輪である
- 事業構想 「面白さ」とは何か? ゲームの神様が語る
- これからのビジネスの肝「おもしろさ」を定義する12のパターン
緊張や不安をコントロールするマインドフルネス
緊張や不安は意識が過去や未来に向いてしまう事で起こります。
「今」に集中するマインドフルネスを取り入れる事で、緊張や不安はコントロールすることが出来るようになります。
Googleなどの大企業でも取り入れられ、緊張と隣り合わせの演奏家たちも実践しています。
緊張や不安に悩む人は是非お試しください!
【マインドフルネス書籍】