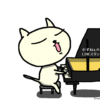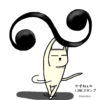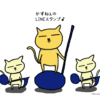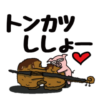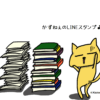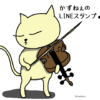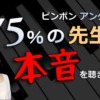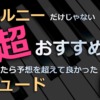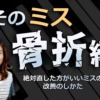【簡単に音楽になる!】古典派ソナタの学び方の3つのポイント~ソナタ形式と和声と調性~
古典派のハイドンやモーツァルト、ベートーベンの音楽ってどうやって理解するの?そんな疑問はありませんか。
古典派の音楽は「形式」がとても簡潔で分かりやすいのが特徴です。
西洋音楽はバロック・古典派・ロマン派・国民楽派・印象派・近代・現代の時代区分が合ってそれぞれに音楽の特徴や傾向がありますが、古典派の作品は比較的「型」が決まっているソナタが多くあります。
古典派を境に形式が複雑になっていったりまた形式すらないものもありますので、まず古典派の形式を学んでおくと、ロマン派やそれ以降、またバロック音楽への理解も広がります。
この記事では古典派ソナタを演奏する時に必要な下準備を以下3つ解説します。
今回は古典ソナタに取り組むときに「コレをおさえておくといいよ!」という3つを解説していきます。
- ソナタの構成を分かる
- 機能和声を理解する
- 転調を分かる
この3つを押さえて楽曲分析をすると8割くらい音楽の作り方が分かるようになります。では解説していきます。
【簡単に音楽になる!】古典派ソナタの学び方の3つのポイント~ソナタ形式と和声と調性~

【簡単に音楽になる!】古典派ソナタの学び方の3つのポイント~ソナタ形式と和声と調性~
古典派のソナタは音楽の形式や楽曲分析のやり方を学ぶのに最適です。
形式やさまざまなルールが比較的分かりやすいのが特徴。
なので逆を言えば、形式を分かっていなければその音楽にならないということです。
ではソナタを学び演奏するために必要な3つのポイントを深掘りしていきましょう。
- ソナタの構成を分かる
- 機能和声を理解する
- 転調を分かる
ソナタの構成を分かる
ソナタは提示部・展開部・再現部という形式で書かれています。
図解するとこんな感じです。

提示部と再現部は同じ「パン」という素材です。
よく「サンドイッチ」に例えられることがあるのですが、調整や若干フレーズに変化があるので、その違いをここでは「バンズ」に例えています。
展開部は味がギュッと凝縮されたハンバーグなどの具です。
他の提示部や再現部と比べてこんなところが一般的には特徴です。
- こまかく変化する
- 要素が多い
- 経過的な転調をする
機能和声を理解する
古典派はの時代は和声を体系化することでシンプルに分かりやすいものにしました。
機能和声における和音の役割や色合い、相互の力関係を理解することで、
どうやって演奏したらよいか
が分かるようになります。
各和音の機能のキャラはこんな感じ。

このキャラが分かることによって自然に聴こえる音楽を作っていくことが出来ます。
- D(ドミナント)⇒T(トニック)の進行でほっとした感じで弾くこと
- サブドミナント(S)はD→T 進行を滑らかにやわらげる
- サブドミナント(S)は音楽に様々な色付けをすること
- ドミナントには緊張感・トニックには安定感
転調を分かる
曲の途中で雰囲気が変わるのの一つが「転調」です。
調性には「色」があります。
それが少しかわるのか、ガランと変わるのかによって表現も変わってきます。
少しかわるものは「近親調」、ガランと変わるものは「遠隔調」に転調しています。
近親調は共通の音が多い調、遠隔調は共通の音が少ないので変化の仕方が違います。
例えるならこんな感じ

似たような名前なのか、全く別の名前なのかというのに例えることができます。
楽曲中の「転調」のポイントをしっかりと変化を表現することで、かなり音楽の表現が「らしく」なります。
まとめ
8割は音楽になる古典ソナタの押さえておくポイント
- ソナタの構成を分かる
- 機能和声を理解する
- 転調を分かる
解説しました。
楽曲分析はこの3つのポイントをふまえて行います。
形式で出来ている音楽は「ノリ」や「感覚」だけでは理解しにくいので、ちゃんと構造を分かってから感覚に落とし込むことが大事です。