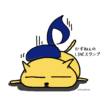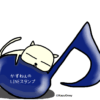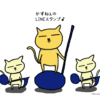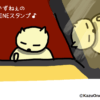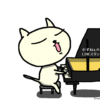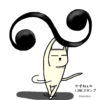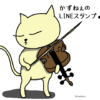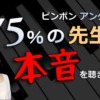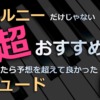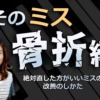【ココが違う!】コンクール入賞者の3つの共通点
今回はコンクールの入賞者の共通点についてお話していきます。
※ここでお話する内容はトップクラスの国際コンクールではなく、国内で開催される比較的だれでも参加できるタイプのコンクールについてです。
コンクールに入賞する人たちはいったいどういった練習をしているのか、自分も一生懸命練習しているのに、評価されないのは何故なのかという悩みを持っている人も多くいるのではないでしょうか。


入賞者たちの共通点とは。もしそれが分かれば、自分が頑張れるきっかけを見つけられるかもしれませんね。
結論から言うとこの3つがポイントになります。
- 技術的なポテンシャル
- コンクールに向けての優先順位
- 徹底した妥協のない練習
では解説していきます。
【ココが違う!】コンクール入賞者の3つの共通点

【ココが違う!】コンクール入賞者の3つの共通点
ここで解説することをやったからと言って必ず入賞するというわけではありません。
しかし入賞のボーダーラインを超えるために入賞者たちが最低限クリアしていることがあります。それをいかに超えてやり抜くことが出来るかで差がでます。
極論に感じるかもしれませんが、コンクールに入賞するためにはかなり振り切れた価値観を持つことが要求されます。
実際、私が出会ってきたコンクール入賞者の方は「すげぇ…」と感じる価値観や妥協のなさ、どこかリラックスしているようで、スイッチが入るとすごい集中力を発揮する能力持った人が圧倒的に多い印象です。
しかし、ストイックに追い込むタイプもいれば、まったく普段の延長上にコンクールがあるという人もいます。人それぞれに違う部分もあります。
ここではどんなコンクール入賞者の場合でも持っている3つの共通点について解説していきます。
- 技術的なポテンシャルの高さ
- コンクールに向けての優先順位
- 徹底した妥協のない練習
1.技術的なポテンシャルの高さ
コンクールの受賞者たちは基礎的なテクニックに不安がありません。
不安のないテクニックとはどういう所で聞かれれるかというと
- 音の粒が揃っている
- 音の密度や軽やかさなどの音色のパレットが豊富
- テンポやデュナーミクのレンジが広い
- 音楽の流れに影響するようなミスタッチが少ない
基礎練習がどれくらい弾けるかでもある程度の目安になります。ハノンやスケールアルペジオのテンポも参考になるでしょう。
スキルアップを目指すための目標値として以下は16分音符を演奏する時の四分音符1拍のメトロノームの数値を参考にするとよく分かります。
- 初級…120~132
- 中級…144
- 上級…160
- 最上級…176
だいたいレベルごとのエチュードに表記されているテンポが目安と考えてください。
しかし!このテンポで弾けたとしても演奏スキルが100%だというわけではありません。テンポをあげても粒が揃っていなかったり音が抜けているのは弾けているうちには入らず、一定時間連続で演奏できるかどうかも大事です。
2.コンクールに向けての優先順位
休みの日や長期休みは上手なのに、学校が始まるとなんか演奏がうまくまとまらない…そういうことを感じたことはありませんか?
コンクール入賞者の多くはこの現象に気づいていて当日に向けて必要なことの優先順位がはっきりしています。そして徹底したスケジュール管理が出来ています。
就学中の子供には学校へ行かなくてはならい義務があり、その中でスケジュールを立てるには策略が必要となってきます。
なぜなら学校ですごす時の頭のなかと、ピアノを真剣に弾いている時では違いがありすぎて、学校での時間が長くなるとなかなか「ピアノ脳」にならないからです。
入賞した人たちと普段は同じように弾けるのに、入賞できるかできないかに大きく影響する一つは本番までの運び方にあります。限られた時間とやらなければならない事の取捨選択を迫られることも多くあります。
3.徹底した妥協のない練習
コンクールはその特性上、演奏に優劣を付けられてしまうものです。
音楽的であるかは一定のレベルを超えると聴き手の好みの領域にあるので審査員との相性もあります。しかし技術での優劣は付けやすいので以下の3つで技術面はすべての人に分かりやすく優劣をつけられています。
- テクニックの高さ
- ミスのなさ
- 完成度
ミスをなくす練習を徹底して行うとそれまで表現しづらかった部分も楽に弾けるようになり、実際に本番での「ミスの有無」というより「聴き映え」に大きな差がでます。
入賞者の多くは徹底してこの練習を積み上げています。
まとめ
小さい子供の場合は選曲によっては基礎を積まずに入賞することもあります。しかしその場合、慢心して基礎を積むことをしなければ残念ながら小学高学年以降の成長が難しくなります。
またコンクール入賞に執着しすぎてしまい、就学中にコンクールだけにスポットを当てたピアノ教育や学習というのは先生と親のエゴに過ぎず、まったく子供や生徒さんのためになりません。
将来的に長く演奏をしたい、音高音大へ進みたい。その教育上の一環でコンクールを成長の一過程であるという位置づけでチャレンジするには大変意義があり、またその上で入賞を目指すというの挑戦する意義があります。
コンクール入賞者の3つの共通点
- 技術的なポテンシャル
- コンクールに向けての優先順位
- 徹底した妥協のない練習
解説しました。
YouTubeチャンネル
演奏動画
演奏動画とトレーニング動画
サイト内関連記事
おすすめ書籍
美しい演奏に欠かせないのが基礎的な技術力の向上です。
演奏にも体幹はめちゃ大事。フォーム改善に一役かってくれます。
緊張や不安をコントロールするマインドフルネス
緊張や不安は意識が過去や未来に向いてしまう事で起こります。
「今」に集中するマインドフルネスを取り入れる事で、緊張や不安はコントロールすることが出来るようになります。
Googleなどの大企業でも取り入れられ、緊張と隣り合わせの演奏家たちも実践しています。
緊張や不安に悩む人は是非お試しください!
【マインドフルネス書籍】