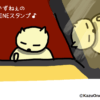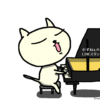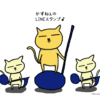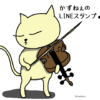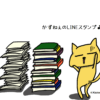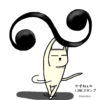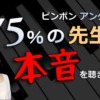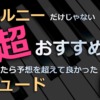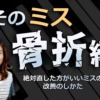【脳科学】練習をサボったら下手になる理由とサボっても下手にならない方法
練習を少しサボってしまったら指の感覚が変わって動かしにくくなったり下手になったなぁと感じた経験はありませんか?
実際には少々サボっても下手にならない人と、少しでもサボると下手になってしまう人がいます。この違いは幼少期から積み重ねてきた時間が関係しています。
ピアノに限らず楽器全般には演奏するための動作があります。演奏は日常生活とは違った身体の動きをします。個人差はありますが楽器を弾くための動きの蓄積量が多いか少ないかでサボった時の違和感が違ってきます。


実際にどうして違和感があるのか、どうして下手になってしまうのかのメカニズムが分かっていると、サボることの抑止にもなるし、サボったとしても無理せず正しく回復させることも可能になります。
この記事ではこんなことについてお話していきます。
- サボれば下手になる科学的根拠
- 幼少期からの基礎の積み上げが鉄壁である理由
- サボったら下手になるのは何故か
- サボっても下手にならない方法
【脳科学】練習をサボったら下手になる理由とサボっても下手にならない方法

【脳科学】練習をサボったら下手になる理由とサボっても下手にならない方法
たくさん練習したら良く指が動くようになるなと感じますよね。一定の量までは練習量と弾いた時の感覚は比例します。なので練習すれば上達する、サボれば下手になるのはあながち間違ってはいません。
弾きにくくなったり下手になったなと感じるのは「練習不足」という一言で済ませることが多いです。
しかし練習不足とひとえに言ってもどうして練習が足りないと下手になるのか?はよくわからないですよね。訳が分からない状態でむやみやたら量をこなしても苦痛に感じるし、リカバーするために無理な練習をして手を痛めてしまった…という話は割とよく聞きます。
サボると下手になる理由を理解して無理なくそして日頃から気持ちを引き締めるためにこの記事の内容をご活用ください。
では以下の4つ
- サボれば下手になる根拠
- 幼少期からの基礎の積み上げが鉄壁である理由
- サボったら下手になるのは何故か
- サボっても下手にならない方法
深掘りしていきましょう。
サボれば下手になる根拠
楽器の演奏は人間の体の本来の動作にはない動きで不自然な体勢で不自然な筋肉の使い方をします。なので何もしなければ楽器を弾く身体にはならないのです。
サボると楽器を弾く身体の動きをしている時間が圧倒的に少なくなってしまうので、反応が鈍くなり下手になってしまいます。
楽器を弾くために必要な身体的な事は主に以下の3つです。
- 楽器を弾くための姿勢を保つ筋肉
- 指や腕など演奏に直接かかわる部分を動かす筋肉
- 筋肉に指令を送る脳
筋肉は繰り返し行う習慣で動作を憶えます。また脳の特性上、頭と体が連動してブレイクスルーするまでは回数をこなしていないと「なかったこと」になってしまいます。
なので楽器を演奏するためには継続的に練習することが欠かせなく、サボると弾きにくくなってしまいます。
では次に演奏に欠かせない「指の独立した動き」について以下の3つのことについてお話していきましょう。
- 指を動かす筋肉について
- 動かしにくい指について
- 演奏者の指は何故独立して動くのか
1.指を動かす筋肉
筋肉は身体の中心の方が多く末端に行けば少なくなります。胸部や肩などに比べると指先は1/10ほどしかありません。
それぞれの筋肉を動かす指令は脳の部位がそれぞれに違っています。
そして指を動かす筋肉は、各指が独立して動くように指令が出されているわけではなく、基本的には一度に複数の指が動くのがデフォルトです。
動かしにくい指
人間の指はそもそもが一本ずつを動かす仕様ではないのに、楽器演奏では1本ずつ独立した動きをしなければなりません。
その時に脳内では
「この指を動かせ」
という指令ではなく、
「使っている以外の他の指を動かさないようにせよ!」
という指令が出ているという驚きの真実があります。
つまり動きを制御した状態が各指を独立させて演奏している時には起こっているのです。
そして最も動かしにくい薬指は、他の指に比べてものすごく「他の指を動かすな指令」が出ているようで、生理学的にも楽器演奏には労力がいる指であることが分かっています。
演奏者の指は何故独立して動くのか
訓練することによってだんだんと「他の指を動かすな指令」に対して脳がフル活動することはなくなり、少ないエネルギーで動かすことができるようになります。
これは指を独立した動きで動かす回路ができあがり、また楽器演奏に適した神経細胞も増えるからです。
楽器演奏の動きをしている時間が長くなればなるほど、神経は増え脳内変化が起こって楽器を弾く脳に変化していきます。
幼少期からの基礎の積み上げが鉄壁である理由
これは2つの点から優位に働くと考えられます。
- アタマが柔らかく神経細胞が作られやすい
- そもそもの積み上げの時間
アタマがやわらかい
幼いころは大人に比べて余計な情報がないので、楽器を弾くことに何の疑問もなく取り組めます。
妙なクセがつく以前に正しく楽器を弾くフォームや楽器を弾く習慣がつけば、後から上書きして修正する必要性がある場合に比べると、格段に脳への負荷は少なく楽に習得できると考えられます。
そもそもの積み上げた時間
育ってからでは基礎的な事や苦労なく動かせる指にするのは全く無理というわけではありません。必要な時間を費やし経験値を積むことができれば指は動きます。
しかし長期にわたる時間の差は、残念ながら埋められるものではありません。
例えば以下で比べてみましょう。
- 7歳から12歳まで毎日30分の基礎練習
- 10歳から12歳まで毎日1時間の基礎練習(1年を365日とした場合)
- 1825日×30分=912時間30分
- 730日×60分=730時間
並べると、ちょっとがんばったら追い付けそうな数字にもみえますね。ですが実際には1の場合は2の場合の始める年齢10歳の時に既に500時間以上の積み上げがある状態です。
そこから2の場合と同じように1時間の基礎練習を積んでいくと、さらに上記より時間の差が生まれます。
- 547時間30分+730時間=1277時間
- 730時間
これだけの積み上げた時間の差があります。
練習した時間によって演奏に必要な指を動かす脳細胞の数が変わってくるのであれば、その差は歴然であると言えます。
育ってからでは無理なのか
演奏は指を動かすだけではないため、それ以外の音楽性であったり音楽を理解する力や表現力と言った他の要素も必要です。
なので指が動く=素晴らしい演奏ということではありません。
しかし表現したい音楽を表現しうるツールを持っているかいないかという点においては、残念ながらハンディがあります。
ですが全く無理ということはありません。
これだけの差があるということを認識してその差を埋めるべく練習を積めるメンタリティがある事の方が大事です。
また足りない事を補うための様々な創意工夫ができるかという所も重要です。
サボったら下手になるのは何故か
一定期間練習することで楽器を弾く脳の回路ができます。
逆に言えば一定期間練習しなければ楽器を弾く脳の回路は薄れてしまうということです。
全く弾けなくなることはありません ⇒ 【関連記事】 基礎練習や譜読みに応用できる脳の有難い能力
脳に限らず人間は遺伝子レベルでもものすごい環境適応能力があることが最近では分かってきています。
しかしサボると脳の回路がだんだんと減ってしまうから下手になってしまうのです。
サボっても下手にならない方法はあるのか
ピアニストの脳を科学する という書籍によれば
音を聴き指を動かす楽器を弾く動作を継続的に続けている人は、少しの間弾かなくても、頭の中で音を鳴らすだけで指を動かして練習しているのと同じような脳の動きをする。
といった内容が書かれています。
これは、継続的に音を聴きながら楽器演奏をすることによって、音を聴く事と指を動かす脳の回路がつながるからだと考えられています。
また、上記書籍の著者のWEB書籍によると音を聴きながら練習することによってこの回路は形成されると書かれています。
この指と耳をつなぐ脳の回路は、20分程度の練習によって作られ始めます。そして、その後の練習を積む中で、指と耳との結びつきは強くなっていきます。しかし、ピアノの音を消した状態で練習しても、この脳の回路は形成されないことが知られています。ですから、指だけ動かしていて、音を聴かずに練習していると、せっかく練習しても、タッチと音を結びつけながら練習するのとは違った脳の回路ができあがってしまいます。
ピアニストのための脳と身体の教科書 より
神経細胞は指を動かし始めて20分ほどで形成されていくようなので、最低毎日20分の練習を心掛け、ある程度の回路が出来上がって強化されれば、ちょっとくらいサボっても影響は大きくないかもしれません。
しかし人間の脳はとてもエコで適応力があります。
サボった状態が続くと
「あ、もうピアノ弾かなくていいんだ」
と脳が判断して楽器を弾く脳の回路は薄くなっていきます。
これがしばらく弾かないと弾けなくなる、弾き続けていない人が弾けなくなる理由です。
まとめ
サボったら下手になる根拠などについて以下の4つ
- サボれば下手になる科学的根拠
- 幼少期からの基礎の積み上げが鉄壁である理由
- サボったら下手になるのは何故か
- サボっても下手にならない方法
深掘りしました。
サボって下手になってしまう大きな理由は、指が動きを忘れないほど強固な脳回路が形成されていないから。
また脳がこの回路は必要がないと判断するに至る時間が経過してしまったからと言えます。
この脳回路は練習時間によってその強度が決まるので、下手にならないようにするには、練習するしかないということですね。
【サイト内関連記事】 基礎練習や譜読みに応用できる脳の有難い能力
【参考サイト】ピアニストのための脳と身体の教科書 より
ゲーム感覚で基礎力UP!飽きないための基礎練習教材
基礎力を上げるメリットは
- 技術の安定と向上(ミスが減る)
- 指示に近いテンポで演奏が可能になる
- 弾きやすくなる
- 譜読みが早くなる
基礎練習教材は適材適所に利用すると最短で技術を上げることができる優れものです。
しかし基礎練習ってつまらないものが多いですよね…継続が大切なのにつまらない…だからマンネリして飽きてしまうのが悩みどころ。そんな基礎練習をゲームのように様々なバリエーションをこなし達成感を味わいながら楽しく取り組んでみませんか?
こちらのnoteではゲーム感覚で基礎力UPできる基礎練習の様々なメニューと練習方法や取り入れ方、カスタマイズ方法などを動画付きで詳しく解説しています。《練習解説動画7本付き》
実際にわたしが実践してきた練習で生徒さんたちも取り入れることで格段の技術力UPをしています。
リンク先のnoteでは一部無料記事と基礎練習の取り入れ方の動画(約8分)を公開しています。
やってみよう!という方は是非チャレンジしてみてください