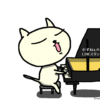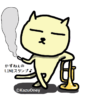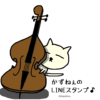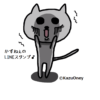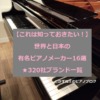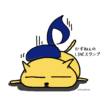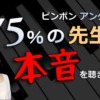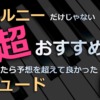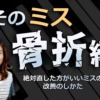【実は最も重要な演奏技術】ピアノのペダルの踏み方
今回はピアノのペダルについてです。
ピアノ演奏技術の中でかなり重要な位置づけにあるのが
ペダリング
の技術です。
ピアノを演奏する時には鍵盤を指で奏でるほかに脚でペダルを踏みます。
ペダリングは音楽の表現や聴き映えに関わってきます。


ペダルの役割を知り技術をマスターして演奏に効果的な踏み方ができるのがベストです。
この記事ではピアノのペダルについて以下のことを解説していきます。
- 標準的なグランドピアノのペダル
- ダンパーペダルの効果
- ペダリングの技術
【ピアニストが語る】ピアノのペダルを踏む効果と踏み方について

【ピアニストが語る】ピアノのペダルを踏む効果と踏み方について
ピアノのペダルは音色を作ったり美しく響かせたり、効果的に音楽を聴かせるためには欠かせないツールです。
しかし使い方を間違うと演奏が台無しになってしまう事もあります。
それぞれのペダルの効果とどういった表現に使われるのかを理解してその技術を磨くことはとても大事です。
では以下の3つ
- 標準的なグランドピアノの3つのペダル
- ダンパーペダルの効果
- ペダリングの技術
深掘りしていきましょう。
標準的なグランドピアノの3つのペダル
ここでは標準的なグランドピアノのペダルについてお話します。
グランドピアノには基本的に3本のペダルがあります。
- ソフトペダル/シフトペダル/ウナ・コルダペダル
- ソステヌートペダル
- ダンパーペダル/ラウドペダル

① ソフトペダル/シフトペダル/ウナ・コルダペダル
色々な呼ばれ方があるペダルで踏むと音が柔らかく少し小さくなります。
踏んでいない状態ではハンマーはピアノに張ってある弦に良く響くよう打弦します。
このペダルを踏むことによって鍵盤が右に動いてすべての弦にはハンマーが当たらなくなり、音の響きを弱く柔らかくする仕組みになっています。
ウナ・コルダとは、1本弦でという意味です。(ウナ=1 コルダ=弦)
現代のピアノではペダルで鍵盤をシフトさせてもハンマーは1本弦にあたる仕組みではありませんが、この呼び名はハンマーフリューゲルなど昔の楽器の名残だと考えられています。
※補足…現代の楽器でも調整によってウナコルダの仕様にすることは可能のようです。があまり実用的ではないためレアです。
使用効果と使用するところ
ソフトペダルともいわれる通り音がソフトになります。
ハンマーの芯からずれて打弦し響かせる減の本数も減らすことによって、sotto voceやppの効果がより表現できるようになります。
また音が固い楽器などでもこのペダルによって音色をコントロールすることがしばしばあります。
② ソステヌートペダル
これは近代以降の作曲家の作品などで使う機会が増えるペダルです。
必要とする音がウナコルダと併用しなければならない箇所などに書かれていることも多く操作が難しいため、ピアニストでもあまり使用しないペダルです。
このペダルは、踏んだ時に鍵盤を押さえている音のみが残る仕組みになっています。
例えば低音に長い音を残しながら別の音域ではスタッカートで演奏することが出来るので、シンフォニックで立体的な演奏が可能になります。
しかし踏むタイミングを間違えるとスカをくらってしまうため、ダンパーペダルの技術内で踏む奏者が多いです。
あまり使用されないためか、調整がうまくいっていない楽器にもたまに出会います。
③ ダンパーペダル/ラウドペダル
一般的にピアノのペダルというと、ダンパーペダルの事を指すことが多いです。
このペダルは踏むとダンパー(弦の響きをストップさせる装置)を弦から離す仕組みになっています。
全ての弦を開放することによって、鳴らしていない音も共鳴してより豊かに響くような効果があり音量も倍増します。
ペダル装置の例外
楽器のメーカーによってペダルの機能が多彩なものがあります。
ファツィオリ、シュタイングレーバーがその代表です。
ダンパーペダルの効果
ペダルは作曲者や編集者によって書き込まれているものと、記載されていなけれど踏むところがあります。
基本的にはペダルを踏むことによって響きは増加しまた立体的な音を作り出すことにも使われます。
ダンパーペダルが使用される意図は以下の4つが挙げられます。
- 響きの増強
- 音を意図的に残す
- 響きの拡散
- 運指の都合
①響きの増強
- フォルテをより響かせるため
- 和音をより響かせるため
②音を意図的に残す
ソステヌートペダルの役割+響の役割
- 手の届かない箇所の低音のロングトーンやを残すため
- アルペッジャーレなどの分散和音の音をすべて残すため
③響きの拡散
ショパン以降、ドビュッシーなどの作品に多いペダル奏法
- 音の粒をすべて立たせずに背景の響として演奏し、メロディーラインだけをそのなかで浮き立たせるような箇所
④運指の都合
メロディラインが運指の都合でどうしても切れてしまうような箇所では、それがペダルであるとは分からないようにつなぎ目で細かくペダルを踏みかえることがあります。
ペダリングの技術
ペダルは必要な箇所に力いっぱい踏むわけではありません。ピアニストはペダルを少なくとも4段階は踏み分け、多い人では16段階くらいは踏み分けると言われています。
段階があるのかと驚かれた方は、もしかすると練習環境のピアノのペダルの調整がされていない可能性があります。ペダルは自分自身で簡単に調整できますので、気になる方は試してみてください。
ペダルの裏側を見てください。楽器本体の接地面にネジがあり、これを調節することでペダルの遊びの部分をカスタマイズできます。

ただし、長期間触ったことがない場合は、かなりカチカチになってネジが回せない場合があります。
そんな時はコレが役に立ちます。
まとめ
ピアノのペダルの踏む効果について以下3つ解説しました。
- 標準的なグランドピアノのペダル
- ダンパーペダルの効果
- ペダリングの技術
ペダルはピアノ演奏においてとても重要なテクニックの一つです。
脚で操作しますが
ペダルは耳で踏む
といわれている程なので、操作が美しいものであるかを常に耳で確認することが大事です。
そして効果的にペダリングができれば演奏は一段と聴き映えが増します。
おまけ
久しぶりにペダルをみて、なんかくすんでるなぁ…と感じませんか?これで磨いてあげて下さい。
ピカピカになってとても気持ちよくペダルが踏めますよ!