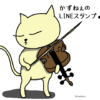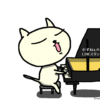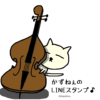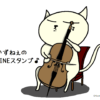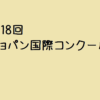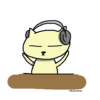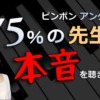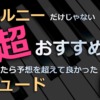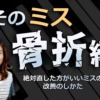【伴奏のコツ】コンチェルト伴奏に求められるピアニストの技量
伴奏は楽しいし、ピアノを弾く人にとっては何より暗譜しなくてよい!ってところでかなり心理的な負担が減ると言う人も多いのではないでしょうか。
しかしいざ伴奏してみると…なんか難しんだけど、どうやったらうまく伴奏ができるんだろうと悩んでいませんか?
この記事ではコンチェルト(協奏曲)をピアノ伴奏で演奏する時に大事なことをお話していきます。
結論から言うとコンチェルトの伴奏はピアノ譜だけではなく原曲のオーケストラの音を知って、オケっぽく聴こえるように工夫する必要があります。
ピアノを勉強して高校生くらいになると他の独奏楽器の伴奏をしたりしますが、ソロでピアノの音しか知らないとなかなか音楽にならない…なんてこともあります。
また大学生や学校を出てからも、コンクールやオーディションなど、ピアノでの伴奏分野で演奏される機会の多いのがコンチェルトの伴奏なので、是非このポイントは押さえておいて欲しい所です。


オーケストラと独奏楽器のための楽曲をピアノで演奏しなければならないのでオケパートをピアノで弾く事になるのですが、このときに大事な3つのことは以下です。
- オリジナルのオケの音を聴く
- オケのスコアを見る
- それっぽく弾く
では解説していきます。
【伴奏のコツ】コンチェルト伴奏に求められるピアニストの技量
コンチェルトの伴奏は、もとはオーケストラが担うパートをピアノで演奏します。
なのでそもそもをピアノで弾くように書かれた室内楽のソナタなどとは、楽譜の書かれ方が違っています。
また出版社によってリダクション譜もかなり違うため、ただ楽譜を見て弾く以外に勉強しておかなければならない事があります。
ではコンチェルト伴奏に必要な大切な3つさらに深掘りしていきましょう
- オリジナルのオケの音を聴く
- オケのスコアを見る
- それっぽく弾く
オリジナルのオケの音を聴く
コンチェルトの伴奏はもとはオーケストラパートで沢山の楽器の音をピアノで演奏します。
オーケストラのバージョンではどういった雰囲気があるのかを分かっておく必要があります。
楽譜だけでは分からないことが、オケの音を聴くことでかなりイメージが湧くようになって、ピアノ譜で演奏したときの雰囲気を作りやすくなります。
またスコアとリダクション譜を見比べた時にも音のイメージをしやすくなります。
スコアを見る
コンチェルト伴奏ではオーケストラパートをピアノで演奏するためにリダクションされている譜面を見て弾きます。
ピアノ用に書かれた楽曲のように演奏すると雰囲気が崩れたり、全然別の曲になってしまうことが多々あります。
書かれた音型がどの楽器が演奏しているのか、パート譜をそのままに使用しているのか、ピアノが弾きやすいように変えられているのかを分かっておく必要があります。
オケの音を聴いてスコアを見ると、リダクション譜のこんなことに気づきます。
- 分散和音は実は分散和音じゃない
- 目立たせる音や模様のようにぼやかす音が良く分かるようになる
- 音域によって楽器が変わるので音色を変えて弾く必要性に気づく
- 各楽器が持つ特性と特徴的な音型が分かるようになる
- 出版社によって、ピアノで演奏することを重視しているか、出てくるサウンドをオケっぽくすることを重視しているかが分かる
それっぽく弾く
上記をふまえ楽譜上の音をオケ楽器での演奏の雰囲気を表現していきます。
リダクション譜でのピアノの伴奏は本来のオケ伴奏で聴く音とは違う雰囲気になってしまう事がしばしばあります。
そのままピアノ伴奏として演奏してしまうと音が立ちすぎてしまうので、オケで聴いた雰囲気の再現に気を配る必要があります。
こんなことに気を配ります
- オケで良く聴こえる音
- 伴奏やオブリガードがどの程度どんな音色で聴こえているのか
- 楽譜中の音楽記号はどういう意図で書かれているのか
スタッカートやスラーも弦楽器と管楽器では全く違う扱いになります。
その雰囲気になぞらえて演奏することが大切です。
まとめ
ピアノを習ってきた人に共通することですが、すべての音をしっかりとらえて弾きなさい。音は抜けないように。音の粒をそろえて。といった注意を受けることが多いので、すべての音を弾きすぎる傾向があります。
全ての音をピアニスッティックに弾いてしまっては、コンチェルト伴奏ではソリストの邪魔になります。
協奏というよりは競争のように聴こえてしまいます。
コンチェルトという本来はオケという響きの豊かな演奏形態で演奏される伴奏においては、少し奏法が変わると考えて演奏するのが良いかと思います。
コンチェルト伴奏に必要な3つのこ
- オリジナルのオケの音を聴く
- オケのスコアを見る
- それっぽく弾く
解説しました。
YouTube
演奏動画
レッスン・トレーニング動画
サイト内関連記事
おすすめ書籍&グッズ